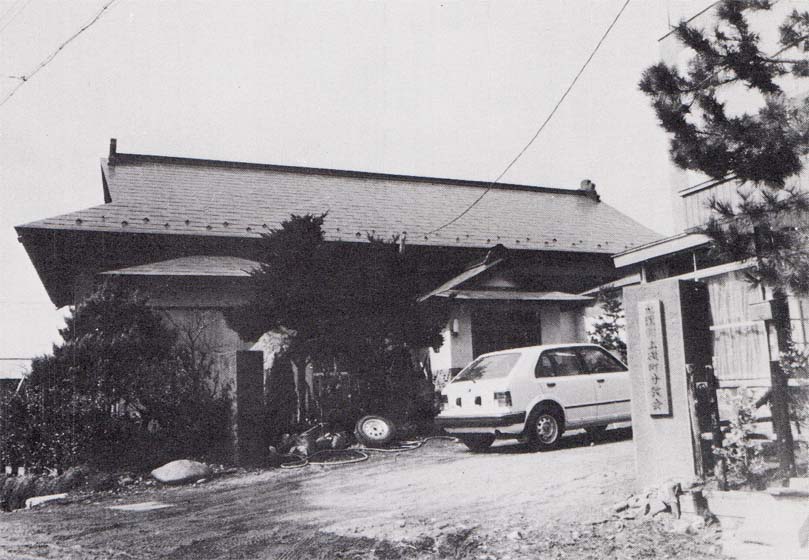=その他の宗教=
=天理教=
明治33年3月、上磯町に布教された。
天理教とは、天保9年(1838年)、大和の農婦中山みきが創唱した現世利益を説く教えとして出発したも
ので、主神は当初、仏教系の転輪王と称したが、やがて記紀などの神を総合した性格を持つ「天理王命」に
改めて神道化した。
明治維新新政府の神道区国教化政策に妥協し、日清、日露戦争前後を通じ、献金、奉仕などをもって国家
主義政策にも協力し、明治41年には独立の教派神道となった。
明治丗三年三月少講義工藤文吉初メテ茂辺地ニ設置布教ニ従事ス。明治四十二年九月三日、道庁ヨリ教会設置ノ許可ヲ得、現今信徒
漸ク大トナル。毎年一月十日大祭ヲ行ヒ、月次祭ハ毎月十二日ニ行フ。 (大正6年『函館市庁管内町村誌』)
明治33年に伝道された新宗教としての天理教も、この大正6年の頃には「現今信徒漸ク大トナル」と
いうように、相当数の信徒を有するようになっていた。
昭和期の天理教
「全町に亘り路上や下水の掃除奉仕をする」(「渡嶋上磯新聞」昭和8年5月20日)というような掃除
を通して積極的な奉仕活動を行い、日中戦争に突入した昭和12年以降は、国防献金造成のため資金調達を
目的にした活動写真会を開催するなど活発に展開していった。
天理教は新宗教とはいえ、その行動においては、既存の神社や仏教寺院と全く異なるところがなかった。
=金光教=
安政6年(1859年)頃、岡山県地方に生まれた金光大神・川手文治郎(1814年〜1883年)を教祖とする
金光教が、北海道に布教開始したのは明治24年、矢代幸次郎によってである。
上磯町には大正13年、函館教会で修業していた浅野民治が上磯教会長となって伝道を始めた。しかし、
その意に反し、上磯周辺の信奉者を数多く集約することができず、昭和2年には同教会を解散。浅野は
この後、網走教会で教勢の拡張に専念することとなった。